「……すごい」
リーが思わずといったふうに感嘆の声を上げた。
「これだけあったら、一生飢え死にしなさそうじゃないか?!」
珍しく興奮気味のリーが辺りを見回している。
この部屋はかなり広く、家くらいなら難なくすっぽりと入りそうなほどだった。
さらには縦向きに設置された大きな棚が幾つもあり、そこには食料の名前が記入されたプレートを付けた箱が所狭しと収納されている。
「ここは備蓄倉庫ですか?」
「そうだ!やはり、君たちは良い反応をするな」
それはつまり、そういった物事とは無縁の生活だったという事だから、手放しに喜べるものでもないだろう……まあ、新鮮な反応は人生において大事なことのひとつだからな!
「そんな君たちに朗報だ!ここの食料のいくつかを渡しておこうと思う、カバンに空きをつくりたまえ!」
「えっ!?」
「良いんですか?」
ほぼ同時に驚きの声を上げた俺たちを見て、アズサさんは複雑な顔をした。
「軍は自分たちのことしか考えていない……人々に渡らない分、たっぷりと蓄えていた。君たちも持っていくことに罪悪感は抱かなくていい。」
──それに君たちの人生はまだまだこれからが始まりだ、必要なものはくすねて盗むぐらいでいい、こんな世界でもそれで生き抜けるのなら、あらゆる手段を取るべきだ。
「な、なるほど……」
その時思い出した。食糧難になり貧困地域の人々はあっけなくこの世を去っていった。
街ですれ違った人、顔をよく見たことがある人、知り合いに、隣人……死はごく身近なことだった。これだけの備蓄があれば、こと切れた人々のうちの、いったい何人の人生が切れることなく続いたのだろうか。
きっと、それでも全然足りないくらい、人々の数は多いんだろう。かえって、供給した方が争いが起きたかもしれない。
”みんな何もないから奪い合う必要がない”この感覚は、何故かあの小さな町の人々に共通のものとしてあった。
「……それに罪を咎めなくてはならないほど、ここらに人はもう残っていない。秩序は大衆──多くのものを纏めるためにあるものだからな!」
「僕は、ルールがない、常識に縛り付けられもしない、今の方がずっと過ごしやすい……怒られそうだけど」
「ははは!それは良い!どんな環境でも、良さを見出せるものは強いぞ、どこでだって生きていけるからな!」
アズサさんは備蓄倉庫の棚の合間をずんずん進んで行く。俺たちは慌てて追いかけた。あまりにも物が収納されているから、気を抜くと見失いそうだった。
歩きながら、備蓄倉庫の説明をしてくれた。
右端の手前から消費期限が近いものが並んでいる。また直近に使用されたりと、人の目が届きやすい範囲だ。奥の棚は消費期限も長い、その上備蓄をここまで消費するようなことはそう起きない。少々持って行ってもバレない、もし気付かれたとしてもその時には既に時効だろう。
それに備蓄倉庫の管理人が少々ずさんに調査結果を提出しているのを知っている。ここまで大量にものがあれば、きちんと調べる気も起きないからな。その上大幅に変更がある場所でもない、毎度ほぼ変わらないデータを真面目に調べて出す、モチベーションも消失しやすい環境だ!
ちなみに、軍部は資金節約の名目上、備蓄倉庫に管理用のシステムを実装しなかったから人力だ。
「なるほど、僕は、こんなところでは絶対働きたくないな……セナは?」
「……俺も」
アズサさんはそれを聞いて、面白そうに笑った。
「私も何度も辞職を検討したさ!まあ、なんだかんだで続けていたから、こうして君たちにも出会えた訳だが!」
進むうちに徐々に明かりが消えていく、一番奥までくると随分暗かった。
「軍も資金繰りが厳しいらしくてな、こういうところは積極的に消灯している……暗いが、なんとか付いてきてくれ!」
奥の棚は入り口を正面にして壁沿いに設置されていた。そのうちの左の最端付近へ進む。
「ここのエリアは長期保存可能かつ、携行に向いている食料が収納されていたはず……お、あった。これこれ」
棚からいくつか箱を下した。そして箱のロックを、白衣の内側から出したキーホルダーのようなもので易々と解除してしまう。
「それは……?」
「これは、多機能ツールでな、こういった場面で大いに役に立つ……そうだ!自室にある、不要なツール類を君たちにあげよう、どこかで使えるだろう!」
「もう一つ自室があるんですか?」
アズサさんは楽し気に片目を閉じて見せた。
「むしろそちらの方が、自室だ。そちらではとっておきも用意できる、楽しみにしていてくれ!」
「楽しみ、ですか?」
なんだろう。
「これは何だ?……けれど食べられるのは確実そうだ!今すぐ食べてみたい……」
何やら横でリーがものすごく機敏にロックの解かれた箱を開封し、中に収納されていた缶詰をまじまじと見つめている。
「これは、レーションか。料理を缶詰にしたものだな!他にも栄養分を調整し固形や液体に加工したものなど、いろいろセットになっているようだ」
「り、料理……!」
リーの目が、「もう待ちきれない」と言っていた。目は口程に物を言う。
俺も、以前ミツルさんにごちそうしてもらってシンと三人で食べた美味しい料理を思い出して、心が弾んだ。
「まあまあ、落ち着きたまえ!これは大事な時のために取っておくといい。なにせ日持ちするからな!」
「そ、そうか……まあ、そうだろうな……」
リーは肩を落とした、がすぐに鞄に詰め込み始めた。
俺もリュックを下し、そう多くない荷物ではあるが、収納しなおし空きスペースを確保する。
「こっちの箱は……栄養ブロックだ!パウチもあるな。ブロックは軽い。多めに持っていくと良い!」
アズサさんは俺たちが作業している間、別の棚を探し、あたらしい収納箱を持ってきていた。
「パウチ?」
「ドリンク──液状タイプの栄養食品だ!といってもドロドロしているものもある。味は……正直個人差があるな、というよりも好みが分かれる!ブロックの方が味もよく長持ちな上軽量だ、こちらが一般的だが、パウチも持っていくといい!」
リュックに詰められるだけ詰め込み、持ち上げた時の重さに拍子抜けしつつもなんとか背負う。
「……重いな」
けれど自然と顔が緩む。この重さは貴重なものだ。
「楽しみが増えた……!やっぱり人生は食が重要なんだ」
リーが意気揚々と立ち上がる。
「よし、食料は何とかなりそうだな!あとは、箱とロックをこうしてああして……よし元通りだ。これをもとの位置に置いておけばそうそう気付かれない」
箱は俺とリーで分担して置きに行く。
再集合したあと、アズサさんは提案した。
「そろそろおやつが食べたい時間だろう、私の自室に来ると良い、ついてきたまえ!」
「おやつ……ですか?」
「おやつ……!セナはあまり馴染みがないのか?と言っても、僕は周りが食べていたのを見ているだけのことが多かったけどさ……甘くて、おいしい。」
「ああ、おやつなら俺も……そんなに頻繁にではないが、たまに飴とか」
「飴も良いよな……!そういえば、栄養ブロックも甘いものあるような」
「それよりもっと甘くて、幸せになれそうなものを提供しよう!……なに、君たちの話の端々に切ない情報が盛り込まれていたからな……せめて今は楽しんでほしい」
遠い目をしながらアズサさんが言う。
俺たちは甘いものに惹かれて、もう少しお世話になることにした。
「…………!!!」
リーが興奮のあまり、声が出せなくなっていた。
提供されたものは、こんがりと焼き色のついた薄いパンのようなもの……パンケーキ、というらしい、が三枚ほど重ねられている。それに樹液のようなものがこれでもか、というほどにたっぷりとかけられていた。おまけにほわりと揚がる湯気さえも甘い香りをまとっている。
リーは分からないが、俺は初めてみる食べ物だった。香りと、近くにいるだけでも感じる温かさで美味しいものであることは申し分なく理解できた。
「本当はバターも乗せたい……!が、今は入手が難しい……軍の冷蔵品メインの食料庫にはあるかもしれないが、流石にそこは管理が厳しくてな……。そのかわりはちみつはたっぷりかけておいた!」
「はちみつ?」
「このキラキラ輝いている黄金色のとろ~っとした甘くて美味しくて頭がどうにかなりそうなやつのことさ」
「な、なるほど……?」
「ははは!そうだ、飲み物はコーヒーがある、インスタントだが!」
「コーヒー?院の世話係の人が飲んでたような…」
「俺も、引っ越す前まではばあちゃんがたまに飲んでいたのを見たことがある」
調理場近くの小さな棚を探りながらアズサさんは話す。
「君たちは飲んだことがないかもしれないな!……ところで、院とは?」
「ああ、僕は孤児院育ちなんだ」
ふと動かす手を止めながら、アズサさんはこちらを見た。
「そうか……まあ、訳アリではあるんだろうが……」
「僕は両親のことについてまるで知らない。だから、特に思うこともないさ」
リーはあっけらかんと言い放つ。本心は読めなかった。
『ピーッ』
「?!」
突然湯を沸かす機械から音が鳴った。先程紹介されその形状と性能に驚いていたが、音も鳴るのか……
「湯も沸いたな。とりあえず先に食べてくれ!冷めてしまうからな!」
「いただきます!」
リーが意気揚々と声を上げる。俺もそれに倣った。
金属製の見慣れないフォークを持つ。今まで使ったことがあるものはプラスチック製だった、それとは違い重みと微かに冷たさがある。
そっとパンケーキをフォークで切る。蜜が生地の内部まで染み込み、色が濃くなっているのが見えた。
「……!」
口に入れた途端、温かくふわりとした生地がほどけ、蜜がじわりと染み出してきた。強い蜜の甘さの後に生地の香ばしさと甘さが控えめながらも存在を主張してくる。
「……おいしい」
初めて食べる系統の甘味。温かく、甘い。幸せを食べ物で表現するならきっとパンケーキになるだろう。そんな食べ物だった。
「美味しい……すごく美味しいです、これ……!」
「そうかそうか!それは良かった!」
にこにことアズサさんは嬉しそうにこちらを見ている。
何も話さないリーは食べるのに夢中で会話する余裕がなさそうだった。
俺はパンケーキの皿のすぐ横に置かれたカップを見る。外側は青く、黒の縞模様があり小ぶりなサイズ。
ちなみに全員デザインの違うカップが置かれている、これはアズサさんの私物だった。
その中には黒く芳しい、見た目は怪しい液体が湯気をたてながら入っている。香りがとても良い。きっと味も良いのだろうと思い、口を付ける。
「わ、苦い……?」
思わず声が出てしまう。飲み込んだとたん、口の中に強い苦みが広がった。
今まで飲んだことのないものだった。慣れない苦みを和らげようと、甘いパンケーキを一口食べる。
「……なるほど。パンケーキの甘みとコーヒーの苦みが合います」
「そうだろう!これが大人の楽しみ方というやつだ!」
「苦い?」
パンケーキを半分以上食べ終えて一息ついたリーがやっと会話に参加してくる。
リーは赤いカップを持ち上げ一口飲んだ。
「わっ!苦い……!なんだこれ!」
リーはコーヒーの苦味に驚き、慌ててパンケーキを口に運んだ。
「大人はこんなのが好きなのか……?」
「まだ食料供給が安定していたころはこれに砂糖とミルクを入れることもあった。苦みが和らいでこれまた美味しい!」
「多分僕はそっちの方が好きかもしれないな……苦い!」
「そうか?俺はこれ美味しいと思う」
「くっ……セナに負けた……!」
「何の勝負なんだ……?」
「ははは!君たちにも好みがあるみたいだな!」
何故か悔しそうにするリー。口に合わなかったみたいだが残すのは悪いと思ったのか、ごくごくと飲んではパンケーキで中和して素早く飲み切っていた。
再びパンケーキ無言が始まり、静かになる。アズサさんはコーヒーを飲みながら近くの本を取り、読み始めた。何だろう、俺も読みたい……。
読書欲は一先ず置いておき、俺も食べるのを再開しながら、ここまでのことを思い出していた。
地下からまた連絡通路を通った先の棟は技術者や職員たちの住環境スペースになっていた。三階まで上がり、左の端から五番目の部屋がアズサさんに充てられた自室だった。
シンプルながらポストと錠が付いているドアを開けると、狭い玄関と三足ほどなら置けそうな小さな靴置き場がある。室内に入ってすぐ、ほどほどの広さの部屋が二つ──というよりも一枚のドアのない仕切りで区切られた一つの大きい部屋、が正しいかもしれない。
手前の区域には簡易的な調理場と小さな冷蔵庫、そして大きめの食卓机がある。冷蔵庫は俺が貧困地域に移り住む前の家にあったものよりもずっと性能が良さそうだった。 奥の区域は寝室らしくベッドが一つあり、すぐ横に机も置いてあった。上には工具やら書類やらが山のように積み重なっている。
俺たちが着いているのは長方形の食卓机だった。椅子が足りず、俺とリーは「もう使えない」とアズサさんが言っていた巨大な四角い機械を椅子がわりにしている。タオルをクッションとして敷いていたので座り心地は良い。外での生活に慣れきっていて、屋根があるだけでも幸福だから特に不満はなかった。
唯一の椅子は、「クッションが壊滅的なので座らせられない」とアズサさんが言い、本人が座っていた、隠すように。
パンケーキを食べ終え、残りのコーヒーを飲みながら辺りを見回す、住環境は最低限度で整えたようなつくりで、シンプルではあるが過ごしやすそうだ。
俺たちが食べ終わったのを見てアズサさんは読書を中断し、食器を下げてくれた、何から何まで至れり尽くせりで慣れないことだから少しとまどった。
「ありがとうございます、食器洗うの手伝います」
「それはありがたい提案だが、大丈夫だ!これくらいならすぐ終わるからな!」
その言葉通り、さっと洗い物を済ませたアズサさんは再び席につき、なにやら銀色のノートのようなものを取り出した。
「それは何?」
リーが興味津々といったように身を乗り出して訊ねる。
「これはノートパソコンだ!」
「のーとぱそこん……?」
「機械のことだ!私の仕事には欠かせなくてな」
「機械……あっ、もしかしてこれの仲間ですか?」
俺は傍に置いていたリュックから黒色の機械を取り出す。アズサさんののーとぱそこん、とやらよりはずっと小さいが。
「おお、これはまた興味深い……君たちが持っているとは思わなかった。それも機械だ、しかもそれなりに高性能の!ノートパソコンより出来ることは少ないが」
「ああ、これ拾ったんです。……リーが持って行こうって言って。道中出会った方に修理もしてもらいました、使えます」
「ほほう!少し見せてもらっても構わないか?」
俺は頷き、機械をアズサさんに渡した。すると慣れた手つきで起動し、何やら操作をし始めた。
「少し待ってくれ、電波が安定しないみたいだ」
「電波?」
「それに繋ぐと、さらに機能が拡張される!」
「他にも機能があるんですね?」
アズサさん曰く、「位置情報を取得して地図の利便性が向上、いんたーねっとに接続して情報を多岐に渡って検索・収集できる。他様々なさーびすに接続して恩恵が得られる」とのこと。
聞きなれない言葉ばかりでよく分からなかったが、きっとすごい便利になるということなんだろう。
「お、接続出来たみたいだな!よし。これをこうして……」
操作をした後、こちらに機械を渡してきた。
「下にある文字盤を押してみたまえ!文字が入力できる。そのあとこの矢印を押すんだ」
「なるほど」
「リー、やってみたらどうだ?1」
興味が隠せない様子のリーに機械を渡す。普段とは違ってとても慎重に画面を押している姿に吹き出しそうになる。
「結構難しいな、これ。思い通りの文字が入力されないんだよなぁ」
まあいいや、この矢印を押せばいいんだろう?
いいのか。アズサさんは楽しげに頷く。
「よし!きたきた、何……ぱわけーあ?」
「ぱんけーき、って入れたつもりだけど何故かそうなった」
「そのまま直さないところ、とてもリーらしいな」
「説明すれば分かるさ。……というより、何でアズサが読めてるんだ?」
「その矢印を押すと、インターネットを経由して私のパソコンにメッセージが送れるのだ!」
「すごい……!これなら離れていても連絡出来るんですか?旅する時に便利そうだ」
ああそれだが……と少し残念そうな顔をしてアズサさんが言う。
「恐らく、外だとインターネットに接続出来ないだろう。ただ人々が多くいるエリアなら可能性はあるが!」
「エリア限定なんですね……?不思議だ」
「というより、いんたーねっととは何なんだ?」
「うむ。きちんと説明するとややこしくなるが……簡単に言えば、ものとものを繋ぐ力だな!使い方によって、働き方が変わる。検索や情報収集する時は……そうだ、図書館のようなものになるな。インターネット上の情報と、我々を繋いでくれる」
「図書館……?!」
「あ、やっぱりセナが反応した」
「ははは!小説でも情報でもなんでも載ってるぞ!」
「すごく、すごく気になります」
これで、検索してみるといい。こうやるんだ。
アズサさんの言う通りに機械を操作する。指示されたように長方形の枠の中に文字を入力して、虫眼鏡のボタンを押す。
「おお……!」
本、と入れたら本についての事柄がたくさん出てきた。
「暫く色々と調べてみるといい!私は横で仕事の作業を進めるつもりだ、今日は捗りそうだからな!」
「僕は……暇だし寝よう。寝袋敷いても?」
「ああ、それなら私のベッドを貸そう!存分に寝るといい!」
各々目的の行動に移り、再び静寂が訪れた。
俺はいくつか情報を検索しながら、手帳にメモしていった。何か制限がかかっているのか、天使族については閲覧出来ないものや、あったとしても内容がとても少ない。
天使族軍部についての情報がなく(辛うじて引っかかったものは嘘か実か不明だった)仕方なく調べるのをやめる。その後も色々と検索してみながら、代わりになりそうな場所──天使族の中枢部、軍学校や大都市がある街の情報を機械に入っている地図と参照して位置を特定した。全く軍部と関わりがないわけではなさそうだ、ひとまずここを目的地にしたい。
人間軍部が目的のひとつにはあるが、まず距離の近い天使族の方へ向かって確かめたいことがあった。リーについて……以前ミツルさんが言っていたことが何となく気になっていた。軍の関係者が親族にいるかもしれない、ということが。
そのまま向かってすぐ判明するようなことは無いかもしれないが、きっかけくらいは掴めるだろう。リーとしては無関係でありたいみたいだが、安心させる材料になるかもしれない。軍とは一切の関係がない事がきちんと判明すればそれはそれでいいことだ。
メモに調べたこと、考えついたことを記録する。天使族についてはこれ以上調べるのが難しいかもしれない。
次は人間テリトリーのことについて、調べてみるか。適当に今まで読んだ本の題名を検索しながら、他の人が出していた感想を読んで共感したり、疑問を抱いたり、と新鮮な経験だ。今まで本について共有出来る人がいなかった。いんたーねっとが身近だったら、もっと読書を楽しめたのかもしれない。
本について思い返しながら、ふと思う。そうだリヒトさんについて調べてみよう。面白いことが載ってるかもしれない。軽い気持ちで入力し、検索ボタンを押す。
出てきた結果に衝撃を受けた。
誰かが撮ったのか、リヒトさんの写真が画像欄に表示される。間違いなく人間だった。
けれど、これは……いや、たまたまかもしれない。……もしそれが現実だとしたら、ありえない事が多すぎる。
俺は画像欄を見るのをやめ、先程の衝撃は未だ心の隅に残りつつも、リヒトさん本人についてまとめられていた文章を読む。誰が書いたのか不明だが、年齢は数年前の記事の時点で34歳。男性。幼い頃に母親は逃げ出し、暴力的な父親の元で暮らし、17歳の時に家出。それからはジャーナリストとして様々なことをリークさせながら天使族に興味を持ち、天使族テリトリーに潜入。指名手配されながらも各地を巡り、人間テリトリー帰還後は書籍を発行。──家族はおらず、一人暮らし。……なるほど、壮絶だった。
というよりなんでこんなにリヒトさんに詳しい人がいるんだ。下を見ると、本人談。……なるほどそういう事か。
どうやら本人もサイトというものを出していて、そこに書籍化しなかった文章を載せているらしい。全て読もう。読書に没頭するうち、先程の衝撃と”もしも”はきっと俺の勘違いだと、そう思い始め次第に薄れていった。
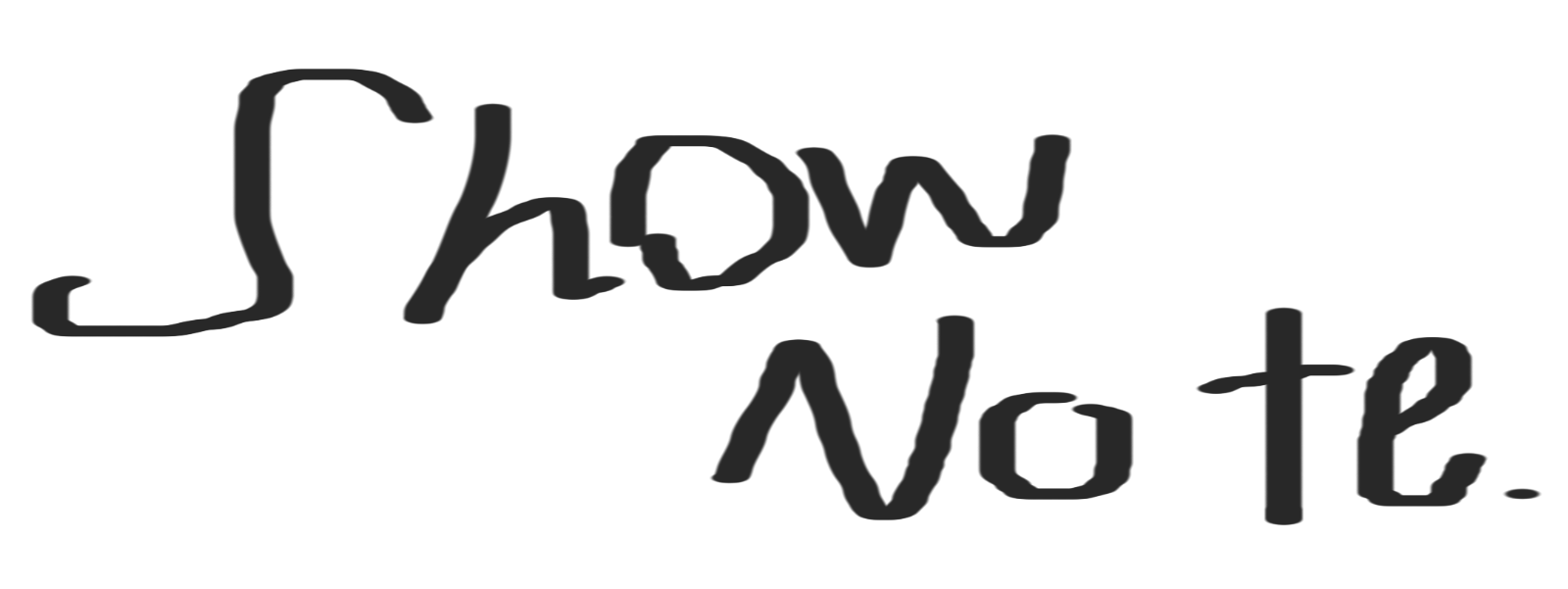

コメント