「そろそろ夕食にしよう、リーを起こさないといけないな!」
いつの間に出ていたのだろう。食料をどこかから調達してきたらしいアズサさんが食卓机の上に食事を並べていく。
「俺が起こしてきます」
機械を机に置く。何とはなしに外を見ればどっぷりと日は沈んでいた。アズサさんの行動も気付かなかった、相当調べものに没頭していたようだ。
寝室──といっても、仕切りで区切られただけの部屋に入れば、リーはすでに目を覚ましていたらしく、ぼんやりと虚空を見つめていた。
そのらしくない様子に胸騒ぎを覚えた。
「リー……?」
返事がない。一層強まる不安を宥めつつ近くまで寄る。それでやっと気付いたのか、驚いたかのようにこちらを見た。
「セナ……?」
「リー、アズサさんが夕飯を用意してくれた。……もしかして、疲れてるのか?」
「あ、ああ……大丈夫。それなりに寝れた、このベッド寝心地良かったしさ」
「そうか……なら良かった。」
「……」
こちらから目線を逸らしたリーが、ぽつりとこぼす。
「やっぱり、趣味は持つべきなのか……?」
「突然だな……どうした?」
「いや、時間つぶしの方法を、寝ることしか知らないからさ……」
俯きがちなリーに、かけるべき言葉が見つからなかった。
「こうやって、安全なところで生活する……そっちのほうを取るべきなのかもしれないけどさ、僕は……危険だとしても、旅に出ていないと、どうしたら良いのか分からなくなる」
「リー……」
「何かの目的を追い続けて……そして外部での出来事が起きないと……忘れることが出来ない、生きる苦痛を」
「……」
「なんてさ……何でもない。忘れてくれ──……そうだ、夕飯は何だろう。君はどう思う、セナ?」
「あ、ああ……とりあえず、食卓に行こう」
頷いたリーはベッドから降り、羽を軽く整え食卓のある部屋へ向かっていった。
俺は先程のリーの言葉を忘れることが出来なかった。
「どうした、セナ?立ち止まってさ……空腹じゃないのか?」
「あ……いや。今行く」
「……早く来ないと僕が全部食べてしまうかもしれないよ?」
からりと笑うリー、先程の沈んだ様子はかけらもなかった。
──これだけ、慣れたように切り替えられるんだ。きっと、ああいうことを考えていたのは初めてじゃないんだろう……
夕飯はたくさん野菜の入った温かいスープと、木の実の混ざった素朴な香ばしいパン。そして焼かれた卵と加工肉を茹でたものだった。
温かいものが食べられるだけでも、恵まれている。それに品数も多かった。
「おなかいっぱいになったなぁ……セナもそう思うだろう?」
「ああ。ミツルさんにごちそうしてもらった以来だ」
少ない食料で今まで育っているから、慣れているとはいえ、慢性的な空腹感──欠乏間はぬぐえなかった。
特に、今まで食事を摂れていたリーは顕著らしく、大抵いつも腹を空かせていた。……身軽に動き回るタイプだから、余計にエネルギーを使うのかもしれない。
「君たち、シャワーを浴びると良い。どちらから入る?」
「し、しゃわー?」
「おお、知らなかったか!シャワーはお湯を出して身の汚れを落とせるものだ!」
「あ、随分前に使ったことがあるような、ないような……」
俺が昔の記憶を引っ張り出そうとしている横で、リーがにやりとしていた。
「セナ、君にも知らないことがあるんだ、って今日は色々と気付かされたよ」
「なんだそれ、皮肉か……?」
「くくっ……違う違う。君に親近感が持てただけさ」
「ほう……今までは違ったんだな」
「君も結構意地が悪いよなぁ……いや、塩対応だ!」
「リーが言葉足らずなんだよ……!」
そんな俺らを見て、アズサさんは大爆笑していた。「君たちはやっぱり面白い!」そう言いながら。
「そうだ、順番……」
「じゃんけんで決めよう。でも、多分僕が勝つから先に入る」
「待て、俺は現実主義だから実際にやるべきだ、と思う」
負けても知らないよ、リーがそう言っているが、それはこちらのセリフだと思う。
「じゃーんけーん……」
ぽん!で出した手は俺がチョキでリーがパー……つまり俺の勝ち。
「あれだけ言っておいて、思いっきり負けてるじゃないか……」
「あれ……いけると思ったんだけどなぁ!」
俺は吹き出しそうになるのをこらえながら、水場に向かった。
「あったかい……」
ほかほかして、気持ちいい。そのまま眠りに落ちてしまいそうだった。シャワーを浴びた時、今までの旅の疲れが、汚れと一緒に落ちていくようだった。
「私と一緒に入らないか?ガールズトークだ!」とアズサさんに言われたリーは「え、絶対嫌だな」と相変わらずの直球を投げ飛ばしてから、そそくさと水場に消えた。
「天使族についての知見を深めるチャンスだったのだが……」
とアズサさんは肩を落としていた。
ほどなくして、リーが出てきた。早いな。
「……驚いた。髪の癖がなくなってる」
「ん?ああ……僕は髪が濡れるとそうなる」
特徴的で、いつも整えないので地味に気になっていた癖毛がどこにもない。
「生まれつきのくせ毛は濡れると直毛になるそうだ!」
アズサさんがワンポイントアドバイスをしながら、入れ替わりで水場へと消えていった。
「あたたかいなぁ……」
満足げに呟きながら、タオルで乱雑に頭を拭くリー、再びくせ毛が出始めていた。
「もう少し、丁寧にやったらどうなんだ?」
「それ、不器用な僕に言う?」
「ああ、そうだった。やっぱりなんでもない」
「そこは否定してほしかったな!」
「はいはい」
俺は机に突っ伏す。このまま眠れそうだった。今は屋根もあって、暖かい部屋の中にいる。何も不安なことがない。いつどんな目に遭うか、そう恐れながら夜を越す必要もない。
けれど、この生活は永遠に続けられるものではない。明日になったら、また旅に戻る。
けれど、そんな生活も良いかもしれない。謎の解明、そしてリーのためにも。
今はただ、しっかり休んで、明日からの旅に備えよう。
「誰が、ベッドで寝るか……うむ!この問題をどうするか……」
けれどアズサさんが問題提起してすぐに、これは解決してしまった。
「僕はもう経験したから」と辞退したリー、そして「寝袋で寝てみたい」と言うアズサさんの要望によって、俺がベッドで寝ることになった。良いのだろうか……?
戸惑う俺を気にしない様子で、すでに二人は寝袋に入っていた。電気を消し、恐る恐るベッドに横になる。
「……もう寝てしまったか?」
「まだです。」「起きてる。」と俺とリーは返す。
「そうか……その、君たちさえ良ければ、君たち自身について聞かせてくれないか?」
いつものアズサさんとは違い、遠慮するような声音だった。
「こんなところに、天使族と人間の若者がたった二人きりで現れた、事情がないと思う方が難しいのだ」
そこで少し間を置き、続けた。
「そもそも、家族……あるいは仲間が居るのなら避難していただろう。各地にそういったものが現れていると聞いている。」
「……そうなんですか?……俺、何も情報を知らなくて……」
「僕も、独りで孤児院を飛び出してきたから、何も知らなかったさ」
一旦静寂が訪れる。どう切り出すべきか、その場の誰もが計りかねていた。
「……僕は、単に天使族が嫌いなだけだ。あいつらの仕打ちに、これ以上は耐えられない、そう思っただけさ。」
「そうだったのか……」
そういうこと。抑揚のない声でそう伝えた後、リーはもう話すことはない、そうとでも言うかのごとく眠り始めた。
「……リーは話してくれないんです。何があったのか、とかを」
「そういうことは言い出しにくいからな……まだ傷が癒えないんだろう……」
君もまだ傷は癒えていないかもしれないが……セナ。
控えめに切り出したアズサさんに俺は応える。
「俺は……俺の家族は、皆、いなくなりました」
小さく息をのむ音が聞こえた。じわじわと”あの時”を思い出し、つめたい風で冷やされているかのような感覚に陥る。
「父は、おそらく戦争で……軍人だったので。妹と、養い親だった血の繋がりはない祖母──二人は、病で亡くなりました」
母は、分かりません。会ったことがなく、父とは話しをする時間がなかた……というより、俺はまだ幼くて、よく分かっていなかった。
「そうか……そうだったのか……──ありがとう、辛いことを話してくれて。私の興味本位であったというのに……」
「いえ、大丈夫です。アズサさんには良くしてもらったので俺たちのことについて伝えておくのが道理……──それに、向き合わないといけない現実だ」
……リーにミツルさん、そしてアズサさんにも自らの来歴について話すことになった。
それによって少し整理された部分もある。現実をいくらか客観的に見れるように──直接的に回想して再び悲しみに沈むことが減り、明文化という一枚の壁を通して物事を見ているような、そんな感覚が得られるようになっていた。
「明日、君たちは旅立つだろう。その道程が幸多きものとなるよう祈ろう……また、何かあったら遠慮なく私を頼ってくれ。」
頼もしいです。そう伝えた俺の言葉に、アズサさんは静かに笑い返した。
「おーい、起きるんだ!穏やかな眠りを断つのはいささか忍びないが……日がすっかり上りきっているからな!」
「?!」
俺はアズサさんの呼びかけを聞き、飛び起きた。何だか、以前もこんなことがあったような……
「うわっ…… !もう昼?!」
部屋の中は暖かな明るさで満ちていた。ベッドの下では豪快に寝袋からはみ出したリーがすやすやと心地よさそうに寝ている。俺は寝袋を容赦なく剥ぎ、リーを揺すった。
「起きろ、リー。……とっくに昼だ!」
「ははは!よく寝られたのは良いことだ!」
アズサさんはうんうんと頷いている。
「……ん?ああ……あとごふん……」
「リー!リー起きろって!」
「そうだ、リー!時間があまりないからな!」
「え……?それってどういう……」
「朝食を摂り次第、君たちは出立すべきなのだ!というのもだな……」
中々起きないリーを一旦置き、俺はアズサさんの話を聞く。
内容はこういったことだった。
朝、まだ俺たちが眠ってた時間に、アズサさんは仕事の会議に参加していた。その議題は”侵入者について”。あれ以来警報も作動しないことから、逃げたか、隠れているか。若者二人組だから放っておいても支障ないのではないか、いや、スパイや窃盗の可能性もある──と終わりの見えない話し合いがしばらく続いたのち、「他にも仕事がありすぎてそれどころではない」と一旦保留になったという。
「まあ、そこまでは良い。問題はここからだ」
施設管理職のとある職員が業務の軍設備データ確認をしていたところ、アズサさんの部屋の水の使用量が甚だしく増加していることを認知した。
「その職員曰く、設備の故障かもしれないから点検させてほしい、とのことだ。……いや、これは故障でもなんでもなく、ただ単に”使用量が増加した”という事実があるのみではあるが……」
その時にアズサさんは、「猫を洗っていた」と説明したらしい。
「猫……?それで大丈夫なんですか……?」
「まあ、基地に住み着いた猫たちのことを良く思わないのはトップの人間だけだ。基本的に職員たちは士気が上がる、そういった声も上がっているから、上層部も渋々見て見ぬふりをしているのが現状だ!」
そんなこんなで窮地は脱した、と思いたかったが……。
「職員は”念のため点検はしておきたい”とのことだ……早くて午後にはここに来るだろう」
「じゃあ……」
急がないと……!思わず、声が上ずってしまう。
「くくっ……セナが動揺してる、珍しいなぁ。……というかねこはないんじゃないかな、アズサならもっとうまく言い訳できたんじゃないか?」
「おお!おはよう、リー。確かにそうだな……私としたことが柄にもなく動揺してしまっていたようだ!」
だが、職員も私に秘匿の疑いをかけていた訳ではない様子だった、ごまかせただろう。
「そうか……なら、大丈夫か」
「リー起きてたのか……」
「無理矢理、寝袋はがされたから腹いせに寝たふりしてたのさ」
「子供すぎる……」
「さあ、ゆっくりしたいところではあるが……早めに朝食を摂ってくれたまえ!その後に抜け道を案内しよう」
朝食はいくつかの穀物が混ぜ込まれた丸いパンに加工肉とトマトが挟まれたサンドイッチ、昨夜の残りのスープを再度加熱してカップに注いでくれた。
「温かいものはそう食べれないだろう……時間はないが、存分に食べて糧にしてくれ!」
二人でお礼を言う。
ふと、刻一刻と別れが近づいていることに寂しさを感じた。
この旅は出会いと別れの繰り返しだ。いずれ慣れるだろうか?……なんだか、それはそれで味気ない気もするな。
考えを押し込めるように、スープを飲み込んだ。
食後、アズサさんが「使う予定がない」とくれたツール類を鞄にしまい、荷造りする。いつの間にか洗濯され、きれいになった外套を受け取る。これから着るには暑い、ついでにリュックにしまう。
二人とも身支度を整え、この部屋と別れる時が来た。時間にして一日ほどしかいなかった部屋だが、十分すぎるほどの思い出がそこにはある。
別れの感傷に浸る時間もなく、先に外に出て様子を窺がっていたアズサさんが戻ってきたのを機に、俺たちはそっと部屋から出た。
しばらく歩く、以前と同じような狭く暗い通路を通り、鉄の扉の前に出る。そっと重い扉を開き、中に入る。埃っぽい匂いが鼻を刺激した。
むき出しのコンクリートのような部屋の中を進む。アズサさんの指示通り奥の床にある扉を開けば、はしごが現れた。三人とも慎重に下り、広いガレージのような場所に出る。大型の自動車の隙間を静かに進みながら、ひと際強い光のある場所──外への出口、へ辿り着く。
ここまで体感にして三十分ほど……あっという間だった。
「ここからまっすぐ進めば、壁まで早いだろう!今は昼休憩の時間帯だ、軍人に遭う可能性も低い、今のうちに出来るだけ遠くまで行くんだ」
「……本当に、ありがとうございました」
「礼には及ばないさ!私も楽しませてもらった!」
「そうだセナ、あれやろう。写真、だっけ?」
「ああ!そうだ」
俺はリュックから機械を取り出す。三人固まって、何とか全員画面に写り込む。写真を撮り、きちんと保存した。
「写真か!仲間と撮る、これはとても良いものだな!」
「仲間……」
「そうだ仲間だ……そして友。友達は良いぞ、友情は大事だ!少々の溝や、違いや秘密があったとしても友情は終わらないからな!」
その友情でどこまでも旅したまえ!
アズサさんの言葉にしっかりと頷く。
「あと、その……!最後に、リー、君の羽を触っても良いだろうか……?」
「あ、ああ。分かった」
突然の懇願に戸惑いを見せたリーだが、大人しく羽を触らせていた。アズサさんには直球な振る舞いをするリーだが、恩は感じているらしい。
「あ、ああ……なんてすばらしいんだこれは……!やはりもっと前に言うべきだった、別れの間際だと別れが惜しくなってしょうがない!なぜなら、永遠に触っていたくなる夢心地のようなふわふわ感だから……!!」
「それには、同感です……!」
「セナ!君、賛同してないでアズサを止めてくれ……!」
「よし……!悲しいがこれくらいにしておこう!いつ職員が現れるか分からない。それに私は設備点検の対応をしないといけないからな……リー、セナ、達者でな!また会おう!」
「はい、じゃあ……行ってきます!必ず、また会いに来ます。その時はもっと面白い話が出来るように──色んなことを経験したい」
「──僕も」
俺たちの言葉に、大きく頷いたアズサさん。それに笑顔を返し、俺たちは先へと進み始めた。
二人分の足音だけが聞こえる。
「…………」
きっと別れが寂しいからだ。俺たちは自然と早足になってしまう。
何度も振り返って見た、アズサさんが手を振っているのが見えなくなるまで、何度も。
シンや、ミツルさんとの別れももちろん、寂しかった。けれど、彼らとはそう遠くないうちに再会する約束をした──チカで再び会うと。でもアズサさんは──絶対に、また会いに行くだろう、けれど……それはいつのことになるのか分からないのだ。
別れだからこそ、明るく振舞った。けれど、二人きりの旅路に戻るにつれ、寂しさがじわじわと心に沁み込んできた。
「……天使族テリトリーまで、どれくらいかかるんだろうな」
気を紛らわそうと、話題を振ってみる。
少し先を進んでいたリーはこちらを向くと、複雑そうな顔をして言った。
「さあ……けれど、そんなにかからないんじゃないか」
「……そうか。」
リーも旅は続けたいだろう。けれど、天使族テリトリーに行くのは気乗りしないようだ。
それ以降、再び静寂が訪れる。俺は、無理に会話するのは止め──軍人との遭遇のリスクもある、素早く移動することにのみ意識を向けた。
動き始めたのが昼だったからか、いつもよりもずっと早く日が暮れたように感じる。リーに声をかけ、草木の生い茂る辺りに移動した。
丁度、ぽっかりと木々が生えていない場所があり、そこで夜を越すことにする。
朝食(兼昼食?)の時にアズサさんが用意してくれたサンドイッチの一部を、包んで持たせてくれていた。今日はこれを夕食にしようと思う。
もそもそと静かに食事をする。数時間前のことをひどく懐かしく感じた。
「……食事って、あんなに温かくて、満たされるものだとは知らなかった」
ふいにリーが呟く。
「今まで僕にとって、食事は……セナに比べたら恵まれていたと思う、けれど、生存のためにただただ摂取するような……それに周りからも疎まれていたからさ、僕、肩身が狭かったんだ」
ミツルさんのときも、アズサのときも、今までとは全然違った。
「たとえこれが、危機だとしても、安心が得難いとしても……僕は、この壊れた世界を、歓迎する」
君は違うかもしれないな、世界の崩壊に伴って、失ったものがある立場だろう?
「俺は……俺は、この世界を受け入れきれない」
「君はそれでいいと思う。僕が変わり者なだけだからさ……」
リーはいつの間にか食事を終え、寝袋に潜っていく。
「何てさ、こんな話するもんじゃない……そうだろう?」
「リーが振ったんじゃないか……」
相変わらずの自由気ままなふるまいに思わず笑いがこぼれる。
「くくっ……じゃあさ、もし生活が落ち着いたら君は何をする?」
俺は片付けをしながら、考える。
「そうだな……。やっぱり、本に関わりたい」
らしいなぁ。
想定通り、と言外ににじみ出ていた。
「リーは?」
「僕?……うーん。趣味も、特に好きなことも無……あ、そうだ。」
リーはふいににやりと笑って見せる。
「パンケーキを極めたいかな。アズサのよりもずっと良いやつ……アズサを驚かせるようなやつ、を作る。いや焼く……?」
いや、待て。パンケーキって何でできてるんだ?
「まずそこからだな……というより、そのまえに不器用を克服する必要があるな」
「パンケーキなら黒い焼くやつに乗せればいいだけだからなんとかなるんじゃないか?」
「生地作りは?」
「…………」
やっぱり止めよう。リーはそう言い放つ。いや、相変わらず転身が速すぎる。
「待て……!俺はリーのパンケーキ食べてみたい……それに、練習すれば出来るようになるんじゃないか」
「そうか………まあ、考えとくさ!」
寝袋に完全に潜り込んだリーに倣って、俺も就寝の支度をする。
「けどさ……セナ。僕は旅が好きかもしれない。どこか一つの所でじっとするより、動き回りたい」
「リーらしくて、良いと思う。」
行けるところまで行こうよ。そこからどうするかは、その時考えよう。じゃあ、おやすみ。
リーの言葉に賛同して、俺も目を閉じた。
「すごい瓦礫の山……まさに、山。これ自体が壁にも見えると思わないか?」
リーが驚いたように話す。俺はその”山”を見上げて絶句していた。
「こ、これだけの瓦礫が生じるほどの壁を壊す爆発……一体どういう事なんだ」
人々の技術で可能な範疇なのだろうか。これが崩れる前を想像すれば──なるほど、遠くまで見えたわけだ。幼い頃旧居住地区のそばの街から見たそれを思い出す。
俺はいつ崩れるか分からないような瓦礫の下を進むリーに忠告しながら、それらの圧倒的な質感に息を呑む。
今日は、朝から歩き続けた。開発の間に合ってないような未整備の道は、やや歩きにくい。
前方の壁のようなもの──それが瓦礫の山だと判明し、それらが次第に近づくのを見るにつれ、俺は緊張していった。
あの山を抜けた先はあちらの世界──。
天使族テリトリーに足を踏み入れた人間なんてそういない、向こうでは同胞の助けも得られないだろう。そもそも、リーとの関わりによって意識が薄れてはいたが大半の天使族は人間を毛嫌いしていると聞く。
そう考えればやはり、リーは変わり者だと思う。崩壊をきっかけにしてはいるが、単独で敵地──人間テリトリーに来ている。それがいかにリスクのあることなのか、俺は身をもって知ることになりそうだ。
それでも……確かめたいことや、知りたいことがある。それに、行ったことのない世界に好奇心が刺激されていた。……リーに影響を受けたのかもしれない。
少し前を行っていたリーがふいに振り返り、身振り手振り話しかけてきた。
「この果てしない山を越え──山登り?しないといけないみたいだ!」
「……流石に登るのは危険だ。慎重に瓦礫の隙間を進んで行こう」
瓦礫の山の間には、土地の特徴がほとんどない。迷ったら厄介なことになりそうだ。来た道を振り返り、確認しながら進んで行く。
暫く進めば前方に、がっしりと瓦礫同士が重なり安定したトンネル──というよりも洞窟のようなものが構えた場所に出る。
横に逸れようにも、大型の瓦礫があり、そう簡単に上れなさそうだ。
リーに合図し、頷いたのを見て進み始める。
「うっ!冷たっ……!!」
「な、何があった?!」
薄暗い瓦礫洞窟の間を進んで行けば、急にリーが小さく悲鳴を上げた。
「うわー……濡れた!瓦礫の間に溜まってた水が落ちてきたみたいだ……なんで、僕がいる所に……!」
「な……」
慌てて上を見てみれば、ぽたぽたと幾つもの水滴がいたる所から落ちてきていた。
「ここは危険だ……別の道に行こう!」
「了解……!」
大急ぎで引き戻す。入口に戻り、一旦態勢を整える。
「リー、服は大丈夫か?」
「なんとか。これくらいならすぐ乾くさ、でも……」
でも?。他にも何かあったのだろうか。
心配な俺を知ってか知らずか、リーはにやりと口角を上げる。……嫌な予感がするな。
「濡れたところが冷えて少し気持ち悪い……から、脱いじゃおうかな?」
「それは、それは駄目だ。断じて、絶対に……!」
「わかったわかった!はははは!!」
焦った俺を見て、リーは大笑いしていた。……無趣味と言っていたが、この天使族は俺をからかうのが趣味なんじゃないのか?
「なんてさ、脱ぐほど不快じゃないんだけど」
「じゃあなおさらさっきのは、なぜ……」
「いや、君は想定外のことが起きると良い反応するだろう?」
「意地が悪いな……!」
これは僕なりの友達とのじゃれ合いだから!とからからと笑いながらリーは前へ進む。
「じゃあ、次はどのルートで行く?」
「まったく……その気になれば、リーを置いて行くことだってできるんだからな……その気になれば」
すみませーん。とリーの全く真剣じゃない謝罪を聞き流しながら俺は代替のアイデアを考える。
「この洞窟に辿り着く前に、細い道があった。瓦礫が崩れそうだから避けたが……そっちを試してみるのはどうだ?」
「了解。じゃあ、戻ろう」
しばらく逆に進んで行く。目的の細道の前に立つ。ドン、と鈍い音が少し離れた所から聞こえた。
「……今、瓦礫落ちたんじゃないか?」
「……ああ。」
「よし!じゃあ行こう」
「なぜそうなる……?!」
だって、面白そうじゃないか。
何がだ……。さも当然、とでもいうかの如く言い放ったリーはすたすたと進んで行く。俺も意を決して、後に続いた。
ゴトリ……背後で瓦礫が落ちた音を聞き、肝を冷やした。幸いこの道のサイドに積み重なった瓦礫の高さはそこまでない。落ちる時もずり落ちるような、鈍い音がする。
辺りを慎重に見回す俺に対して、リーは何てことないように身軽に進んで行く。
ふと、視界の右上……リーの真上当たりの瓦礫が滑るように動…
「リー!危ない!!」
咄嗟にリーを引く、思わず羽を掴む形になってしまった。
「わっ!」
ガコンッ!大きめの瓦礫は滑り落ちた後、いくつかのパーツに割れたような音がした。
「うわぁ……」
「もふもふ……?!」
俺はというと、引いた際にバランスを崩したリーが思い切り後ろに下がったため、意図せずその羽に包まれてしまう。
「うわぁ……僕、今日厄日なんじゃないのか?」
「そうなんじゃないか」
「適当だなぁ……!」
「だって、もふもふが……!!」
その時やっと、リーは羽で俺を包み込んでいたことに気付いたようだった。
「セナ、君羽好きだよな」
「だって、もふもふしてるから!──……よし、先に進もう」
このままでいるわけにもいかない、名残惜しいが、羽から離れた。
「うーん、やっぱり僕、君と行動しないといつ死ぬか分からないな」
「もう少し、周りを見るようにすればいい」
「それが難しいんだよなぁ……。」
「俺が先に行くよ」
了解、任せた。
大人しく後方に来たリーと立場を入れ替え、再出発する。
それからも幾度か危険に遭遇しながら、大分進んだ。いつの間にか時間が経っていたらしい。気付けば日が暮れ始めていた。道中見つけた安定した瓦礫の下で夜を越すことに決める。
寝袋に潜り、空を見上げる。
瓦礫に阻まれ、夜空も星空も見えない。それだというのに、何故か高揚していた。
日が昇り次第、さらに先へと進んで行く。そうすれば、そう時間のかからないうちに、あちらへ辿り着くだろう。
この瓦礫の先に──……この自分が足を踏み入れることになろうとは、夢にも思わなかった。
……天使族テリトリーへの到着だけが目的ではない。これからも旅は続くだろう。しっかり寝て明日に備えないと。俺は逸る気持ちを宥め、目を閉じた。
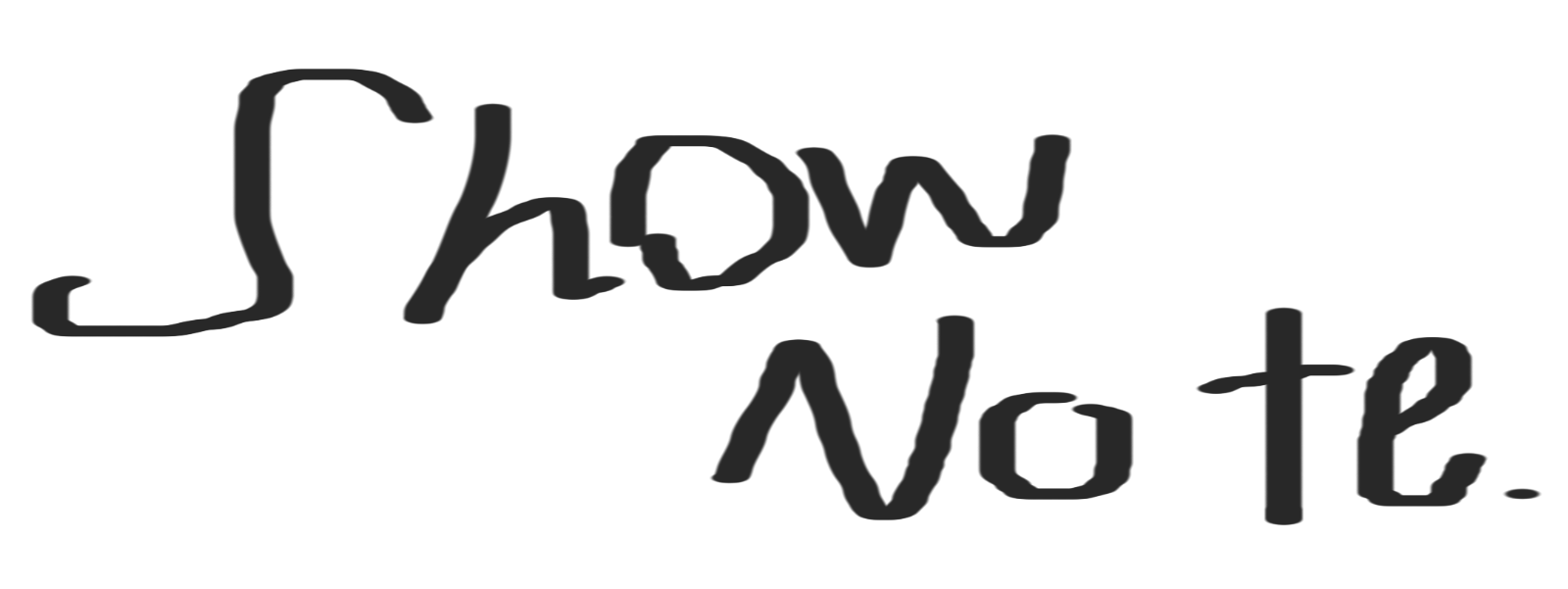

コメント